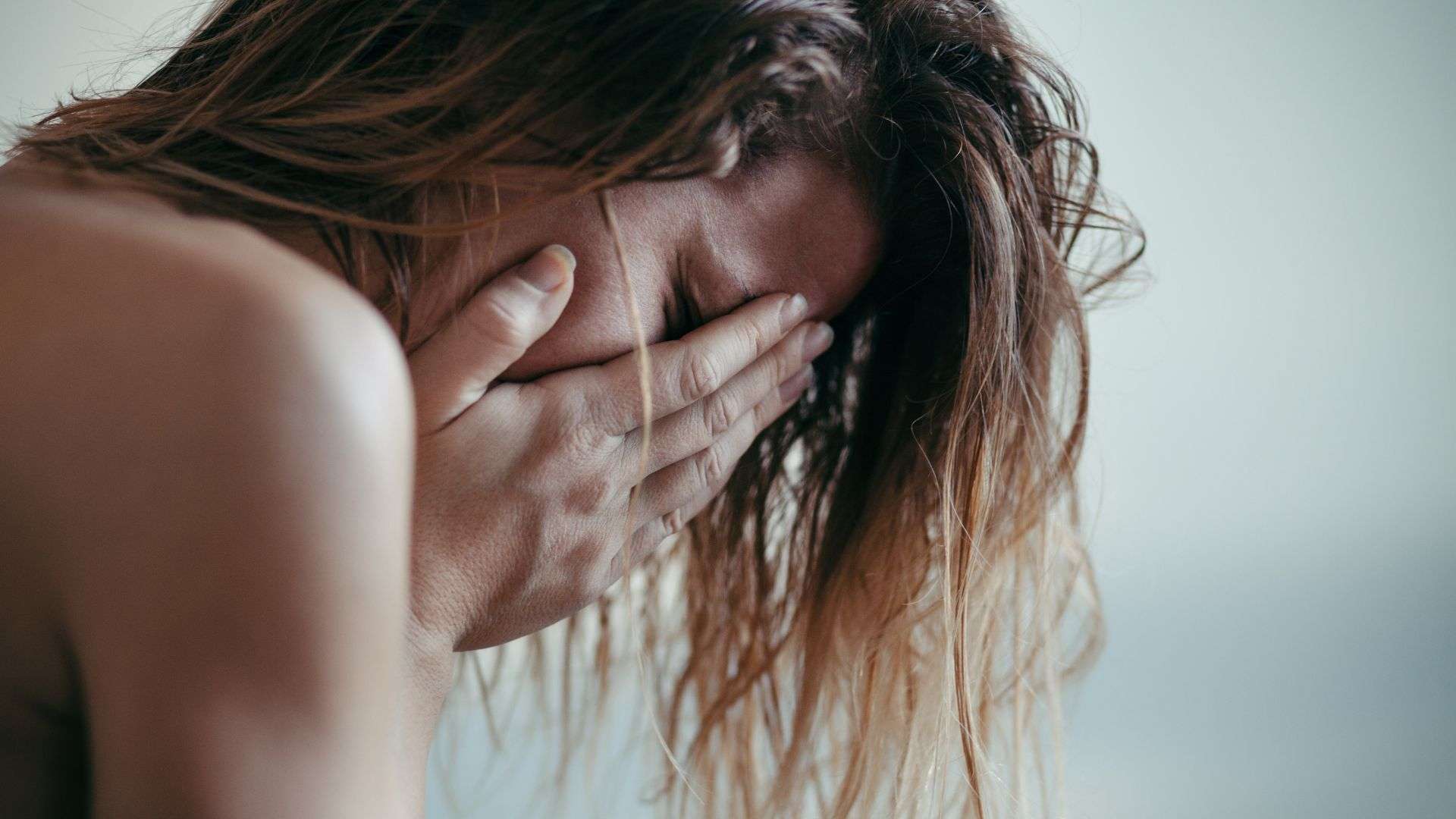【認知症の症状】周辺症状 介護拒否
2024/06/11
今回は、認知症の周辺症状の1つ「介護拒否」についてお伝えしていきます。
「介護拒否」というのは、読んで字のごとく、
認知症の方が介護されるのを拒否するすることをいいます。
具体的には、食事拒否や入浴拒否、トイレ拒否、着替え拒否、外出拒否などです。
お薬を内服することを拒否する、
内服させた薬を吐き出すなどといったことも介護拒否にあたります。
食事の拒否や内服の拒否は、健康の維持に直結するため、早急な対応が必要になってきます。
介護拒否に対応していくためには、
なぜ介護を拒否するのか、その原因を探ることが大切です。
なぜ介護を拒否するのか
認知症の方は、いろいろな理由から介護を拒否すると考えられています。
何らかの意思表示のために介護を拒否するケースもあるため、原因の見極めが重要です。
以下に介護を拒否する主な原因を挙げていきます。
認知機能の低下
認知機能が低下すると、結果的に介護拒否につながることがあります。
たとえば、認知機能が低下して
「出されたものを食べ物として認識できない」
「箸の使い方がわからない」
といったことが起きると、出された食事を食べなくなってしまいます(食事拒否)。
代表例が、食事の方法を忘れてしまい、出されたものを食べなくなることによって起こる食事拒否です。
被介護者には、といった認知機能の低下が起こっています。
羞恥心
介護されていることに恥ずかしさを覚え、介護を拒否する場合があります。
特に着替えや入浴、排泄などの際に起こる傾向があります。
介護をされる側の気持ちに配慮せずに、
むりやり介助をしてしまうとよりいっそう拒否が強くなる場合があります。
これは、物忘れが強い人であっても同じです。
無理やり介助されたことは覚えていなくても、
その時に嫌な思いをした感情の記憶は残っている場合も少なくありません。
自信喪失による心苦しさ
介護を受けている状態を「人に頼っている」と感じ、情けなく感じることから介護を拒否するという場合もあります。
介護者に感謝しているいっぽうで、迷惑をかけている、申し訳ないと感じ、自信を喪失してしまうことが多いようです。
思い通りにならない歯がゆさ
自分の身の回りのことに介助が必要になると、
今までのように自分の好きなタイミングややり方でそれらを行うことができなくなります。
そのため、自由に行動できないストレスから少しずつ不満がたまっていき、結果的に介護拒否に至るということもあります。
新しい環境への不安・戸惑い
施設に入居したり、同居が始まったりすると、それまでの生活から大きく変化します。
食事一つとっても、食事の内容だけでなく、食事をとる時間や量、味付けなど今まで通りというわけにはいきません。
こうした変化に適応できないストレスから、介護拒否を起こすケースがあります。
体調不良
身体の調子が悪く、介助を拒否しているという場合もあります。
体調が良くないから食べたくないとかお風呂に入りたくないと思っていても、ご本人がそれを介助者に伝えられるとは限りません。
いつもは拒否しないかたが介助を拒否する場合には、
体調が変化してこないか注意してみていった方がよいでしょう。
介護拒否への対処法
体調を確認する
介護を拒否する人の中には、その日の体調が悪いことが原因となっていることがあります。
認知症の方の場合、自分の気持ちや状況をうまく伝えることができず、
単純に介護を拒否するという行動をとっていることが少なくありません。
「どこか調子が悪いですか?」「〇〇が痛いですか」などご本人に声をかけ、体調を確認することが重要です。
介護の必要性を本人に伝える
「自分はまだ必要ない」と介護を拒否される方は、自立心やプライドが高い傾向があります。
「なぜ介護が必要なのか」をご本人にしっかりと伝えることは重要です。
そうすることで、少しずつ介護の必要性を理解し、受け入れてくれる場合があります。
本人の気持ちを優先する
まず、可能な限り介護を無理強いせず、本人の意思を尊重することが大切です。
介護する側が感情的になったり、無理強いをしてしまうと、さらに拒否が強くなってしまうことがあります。
可能であれば、拒否をする理由を聞き、ご本人の思いや意思を尊重するようにしましょう。
タイミングを変えて再び声かけする
一度拒否されても、時間をおいてから再度声かけすると、介護を受け入れてもらえることがあります。
これは、気分にムラがあったり、体調が悪かったりして拒否している場合があるためです。
その場で強引に介護を進めるのではなく、タイミングを改めるようにしましょう。
介護する前に何を行うかを伝える
何も言わず、いきなり介助し始めると、相手が戸惑って抵抗することがあります。
介助を行う際は、何をするかを具体的に伝えるようにしましょう。
特に、物忘れが強い人に対しては、何回も声掛けするとよいでしょう。
介護の直前だけでなく、少し前から予告するようにコミュニケーションを取るとスムーズに進みやすい傾向があります。
たとえば、食事の準備を始める前に「もうすぐお昼ご飯ですよ」「ご飯ができたら一緒に食べましょう」などと声をかけるように意識してください。
プロの力を借りる
家族だけでは介護拒否に対処できない場合、行政サービスや介護サービスなどの利用がおすすめです。
家族だけで介護を行うことにこだわると、家族の生活に支障が出てしまうことがあります。
専門家に相談し、必要に応じてデイサービスの利用や施設への入所などを検討すると良いでしょう。
ヘテロクリニックでは、オンライン相談を受け付けています
認知症介護についてお悩みの際には、ご利用ください。
お申し込みは下記リンクから
https://hetero-clinic.hp.peraichi.com/onlin
こちらも参考に